
【退職後の手続き順番】 次の就職先が決まっていない場合
退職するものの、次の就職先・会社が決まっていない状態で退職した場合の手続きについて解説します。
何から手を付けて良いかわからない方も、この順番で手続きを行えば問題ありません。
退職後の手続きには、期限があるものもあります。
どのような手続きが必要かしっかりと確認しておきましょう。

手続きの順番
- 退職後に必要な書類の申請(会社への申請)
- 会社への返却物
- 受け取る書類の確認
- 雇用保険「求職者給付」の申請(ハローワーク)
- 健康保険の手続き(自治体の健康保険窓口)
- 国民年金の手続き(自治体の国民年金窓口)
- まとめ
1. 退職後に必要な書類の申請
退職が決まったら、会社に退職届を提出します。
会社によっては、退職届を提出するときの申請書類に、退職後に必要な書類の申請書があると思いますので、忘れずに申請をしましょう。
1. 雇用保険被保険者証
雇用保険に加入している証明になるものです。
2. 離職票
雇用保険「求職者給付」いわゆる失業保険を受給するために必要な書類です。離職票の内容は、求職者給付「基本手当」の日額と給付日数に関わります。
※基本手当の日額と給付日数についての関連記事・・雇用保険「求職者給付基本手当」とは?失業保険はいつからもらえるのか
3. 健康保険資格喪失証明書
健康保険から、国民健康保険に切り替える場合に必要な書類です。
4. 源泉徴収票
年内に転職が決まらない場合は、確定申告をする時に必要になります。
5. 年金手帳
国民年金の加入に必要です。会社に年金手帳を預けている方。

2. 会社への返却物
お世話になった会社を退職する際に、業務の引継ぎもしっかりと行いましょう。
今まで会社から借りて使用していたものは、退職日の1週間前には整理をしておきます。
携帯電話やPCなどの他に、事務用品なども返却を忘れないようにしましょう。健康保険証は、退職日には返却します。
3. 受け取る書類の確認
退職日を過ぎると、会社から申請した書類が届きます。
申請には期限があるものもあるので、書類がいつ届くのか、前もって会社に問い合わせておくことが必要です。
書類がいつ届くのかわかると、その後の手続きをいつ行うかも計画できます。
4. 雇用保険「求職者給付」の手続き
退職後に、次の就職先が決まっていなくて、雇用保険「求職者給付」を受け取る意思がある場合、雇用保険「求職者給付」の受給の手続きが必要になります。
雇用保険の受給期間は、原則として退職日の翌日から1年間です。
その1年間の間に受給を終える必要があるため、速やかに手続きを行いましょう。
※受給期間についての関連記事・・雇用保険「求職者給付基本手当」とは?失業保険はいつからもらえるのか
■ハローワークへの申請
住んでいる地域のハローワークに失業保険の申請を行います。
■必要書類
離職票、雇用保険被保険者証、通帳、本人確認書類(免許証など)、印鑑、マイナンバーカード、3か月以内に撮影した写真2枚
■受給までの流れ
ハローワークに失業保険の申請を行い、受給資格が決定します。
その後は、7日間の待機期間があり、雇用保険受給説明会に参加します(コロナ期間は、ネットの動画を視聴)。
失業認定日が決まり、ハローワークの来所の日時が設定されます。就職活動をしているなどの要件を満たしていて、失業認定日に来所することで、失業保険の受給ができます。
初回は、失業保険の申請と雇用保険受給説明会への参加で、2回の就職活動をしたこととみなされます。
それ以降は、次回の来所日までの間に2回の就職活動を行います。
自己都合退社の場合は、受給資格決定日から3か月間は給付制限期間があります。事前に生活費などの計画をしておきましょう。
失業保険の申請を行うと、ハローワークの方が、受給までの流れを説明してくれるので心配ありません。必要な書類をしっかりとそろえて手続きにいきましょう。

5. 健康保険の手続き
退職後の健康保険には、3つの選択肢があります。「①国民健康保険 ②任意継続制度 ③家族の扶養に入る」。手続きには、それぞれ期限がありますので、退職前にどの健康保険に加入するか検討しておきましょう。
①. 国民健康保険への加入
■自治体への申請
住んでいる地域の自治体の健康保険の窓口で申請を行います。退職後14日以内に申請が必要です。
■必要書類
健康保険資格喪失証明書、本人確認書類、通帳、印鑑、マイナンバーカード
会社都合の退職の場合は、国民健康保険料の免除などがあります。ハローワークで雇用保険受給資格者証を受け取ったら、自治体の健康保険窓口で申請を行いましょう。
② 任意継続制度
任意継続制度とは、退職後も前の会社の健康保険に加入し続ける制度です。任意継続制度を利用できるのは、2年間に限られています。保険料が全額自己負担になることに注意が必要です。
■加入していた健康保険に申請
退職の翌日から20日以内に申請が必要です。被扶養者がいる場合は証明書類も多く必要になります。
■必要書類
申請書、印鑑、初回保険料、※被扶養者がいる場合は、被扶養者届・住民票・扶養を証明する書類が必要
③ 家族の扶養に入る
年収が130万円未満場合、家族が加入している健康保険の扶養に入れる可能性があります。それぞれの加入している健康保険に要件を確認して、手続きを行いましょう。

6. 国民年金の手続き
会社で勤めていた人は、第2号被保険者の区分で加入していましたが、次の就職先が決めっていない場合は、無職になるので、第1号被保険者に移行する手続きを行います。
■自治体への申請
住んでいる自治体の年金窓口で申請を行います。退職後14日以内に申請が必要です。
■必要書類
年金手帳(基礎年金番号通知書)、離職票、本人確認書類、印鑑
失業状態にある場合は、保険料の支払いの免除もあります。保険料を納めることが難しい場合は、手続きを行いましょう。
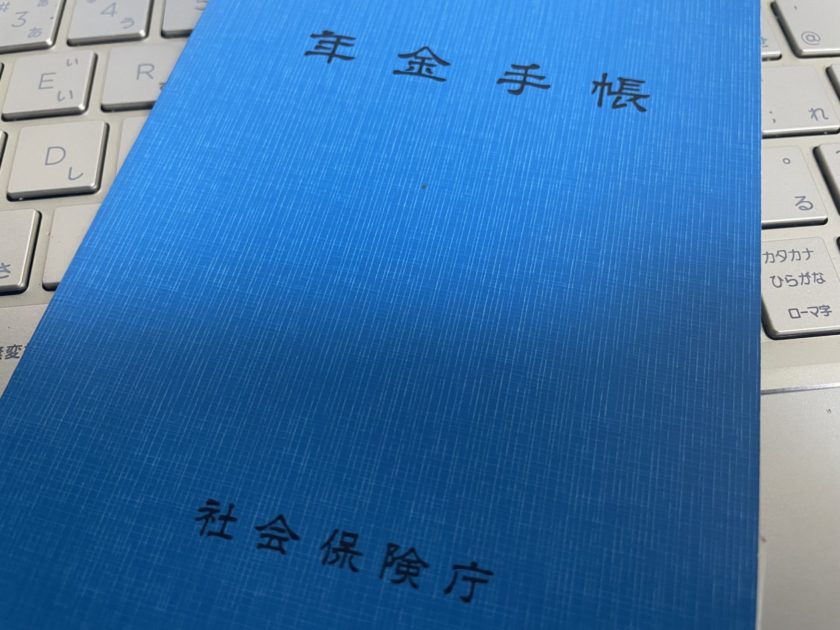
まとめ
退職後に必要な手続きは、あまり経験がない方も多いと思います。
私も2021年3月に20年勤めた会社を退職して、初めて手続きを行いました。
まずは、手続きに必要な書類を退職する会社にしっかりと申請することが大切です。
必要な書類が届いたら、ハローワークと自治体に行って手続きを行うだけなので、あまり心配しなくても大丈夫です。


ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません